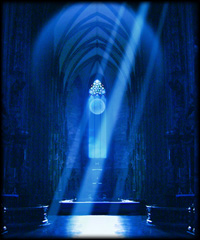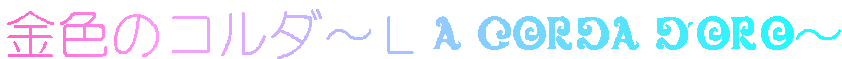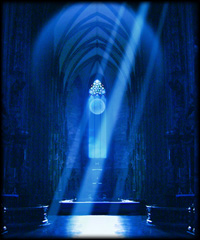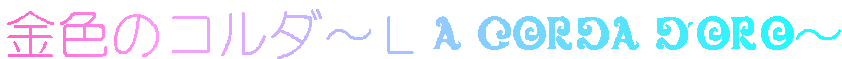彼のことを、好きになればなる程不安になる。
彼の些細な言葉や仕草にさえ、色んなことを勘ぐって。イライラして、不安になって、泣きたくなって。
はじめ、それは小さな種のような物だった。
それがいつの間にか、胸の奥深くに植えつけられていて。
いつ芽を出したのかも分からぬままに。
気がついたときには深く、深く根付いてしまっていた。
その植物を、何と名づけたらよいものか。
際限なく伸び続ける蔓に、雁字搦めに囚われて。
今では、身動きすらもままならない。
あまりにも不安定な感情。
本当は、もうとうに。
その感情の名を、知っている。
知っているからこそ、認めたくない。
認めたその瞬間にでも。
決して抜け出すことの出来ない、深みへと陥ってしまいそうな気がして。
――いや。
本当は。
もうとっくに、抜け出せないところまで来てしまっているのだろう。
だから。こんなにも、苦しい。
時折、思う。
すべてなかったことにすれば、楽になれるのだろうかと。
今更そんなこと出来るわけがないと、一番良く知っているのは他ならぬ自分自身だ。
もしも今。彼が、自分から離れて行ってしまったら。
そう思うだけで、凍りつき、粉々に砕かれそうになる心。
なのに。
それでも猶、思わずにはいられないのは何故だろう。
もし、この恋を白紙に戻せたなら。
この煩わしい感情もなくなるのではないかと。
※ ※ ※
「どうした?」
放課後の練習室。
いつものように、バイオリンの練習をしていた香穂子は、突如耳元で聞こえてきた土浦の声に、弾かれるように顔を上げた。
バイオリンを構えたまま、いつの間にかボンヤリとしていたらしい。予想していた以上に近くにあった彼の顔の思わず息をのむ。
「な、何が?」
「今日はやけに大人しいじゃないか」
「そうかな?」
「ああ。まさか、熱でもあるんじゃないだろうな」
からかうような口調。けれど眼差しは真剣そのもので。そのまま自然な所作で、大きな手のひらを額に当てられる。
触れ合ったところから伝わる温もり。
馴れないその感覚に、自分の顔が急速に熱を帯びるのが分かった。
それを誤魔化すように、慌てて声を絞り出す。
「だ、大丈夫だよ!」
「そうか?…あんまり根詰めすぎんなよ」
本当に心配していてくれるのだと、ありありと分かるような…労りのこもった声。
嬉しいはずなのに胸の奥がチリリと痛んだ。
――最近、頻繁にこんなことがある。
彼の優しさに触れるたびに、混在する嬉しさと切なさ。
矛盾する、二つの感情。
その、理由。
「ちょっと休憩しようぜ」
長い綺麗な指で、ポンポンと悪戯に鍵盤を叩きながら問いかけてくる。
「なんかリクエストあるか?」
「え?」
予想外の言葉に思わず声をあげる。
「それじゃ土浦君の休憩には…」
ならないじゃない。
そう言おうとして、楽しそうに輝いている瞳にかち合った。
時折見せてくれる、子どものように無邪気な彼のこんな表情に。香穂子はひどく弱い。
「なんでもいいの?」
「ああ」
即座に返ってくる答え。
その自信たっぷりな様が、少しだけ憎らしいと同時に誇らしくもある。
「…えっと…じゃあ…『楽しみを求う心』」
すると土浦は一瞬、意外そうに目を見張り――そして微笑んだ。
「マイケル・ナイマンか。――OK」
ポーン…と一つ。
高い音が響いたのを合図に、長い指が、何のよどみも無く鍵盤の上を滑りだす。
切なくも情熱的なメロディが狭い室内に響き渡る。
柔らかな音色に全身が包まれるのを感じながら、香穂子はそっと目を閉じた。
広がる――綺麗な、世界。
この、「彼」だけが作り出せる、情熱を秘めた鮮やかな世界が、香穂子は好きだった。
けれど。コンクールが終わり、こうして共に過ごす時間が当たり前になってから、こんなふうに彼の音に触れるたび、喜びと同時に、常にはなりを顰めている不安が、首をもたげるようになった。
――そのきっかけは、些細なことだった。
『ね、香穂子は土浦君に何ていって告白されたの?』
ある日の放課後、恋愛話で盛り上がっていたのだろう。会話の輪には加わらず、急いで練習室に向かおうとしていた香穂子は、クラスメイトのからの唐突な質問に思わず足を止めていた。
『頬を染めて告白する土浦君なんて、想像できないって皆言うんだよね。あ、それとも告白は香穂子からだったの?』
学内コンクール入賞者同士のカップルということで、大勢の好奇の目が向けられたのは当然といえば当然のことであった。
――しかし、香穂子はその質問に答えることができなかった。
言われて、初めて気がついたのだ。
コンクールが終わって、恋人同士と周知の関係となった土浦と香穂子。だが、その実、2人の関係を決定付ける明確な言葉は、今まで一度だって互いの口から出たことはなかったことに。
あの日、コンクールが終わった後。香穂子は思いの丈をこめて愛の挨拶を奏でた。それに気づいた土浦が、屋上まで急いで駆けつけてくれて。笑顔を見せてくれたときは、本当に嬉しかった。
けれど、「好き」の一言を彼は聞かせてくれなかった。それは、香穂子も同じで。
…もしかして、付き合っている気になって、舞い上がっていたのは自分1人だけだったのだろうか。
気づいた瞬間、愕然として、思わずその場に膝をつきそうになった。クラスメイトたちの期待する視線に耐え切れなくなった香穂子は、その質問に曖昧に微笑んだだけで、逃げるように教室を後にしたのだった。
その不安が、確信に変わったのは、そのすぐ後のことだった。
土浦が同じサッカー部の友人たちと会話しているのを偶然、立ち聞きをしてしまった。その会話の中で、彼ははっきり言ったのだ。
『土浦〜、お前はいいよなー。寂しいときはいつも側でささえてくれる彼女がいるんだからさ』
『…あいつはそんなんじゃない』
…ポーン…
最後の旋律が、柔らかく余韻を残して響き渡った。
それを合図に、香穂子もまた夢想から覚め、ハッと顔を上げる。
鍵盤から顔を上げた土浦の視線が、香穂子とかち合い、柔らかく細められる。
「土浦君…」
愛おしいものを見つめるかのようなその笑顔に、また、勘違いしそうになる。
もう、分かっている。これは、友人に対しての笑顔だ。優しい人だから。誰よりも優しい人だから。いつまでも香穂子があぶなっかしいのを見て、手を差し伸べてくれていたのだろう。そこに特別な感情などなにもなかったというのに。
それなのに浅ましく期待して。側にいて。
自分はなんて、愚かだったのだろう。
ポスン。
軽い音がして、香穂子は無意識に土浦の背中に顔を埋めていた。
今まで終わりを告げるのが怖くて先送りにしてしまっていたけれど、これ以上彼を好きになる前に。
手放すなら「今」しかない。そう思った。
「香穂…?」
戸惑ったような、彼の声。密着しているせいで、その振動が伝わってくる。
――でも、顔は上げない。
今きっと、すごく醜い顔をしている。そんな顔は、見せたくないから。
だからそのままで、彼に告げる。
「土浦君……今までありがとう…」
「え?」
突然の、要領を得ない言葉。
意味を図りかねて、彼が戸惑っている様子が伝わってくる。
それでも今を逃したら、またずるずると今のままの関係を続けてしまう。そう思ったから、かまわずに、香穂子は言葉を続ける。
「土浦君は優しいから…私がいつまでも危なっかしいのを見ていられなくて、手をひいていてくれたんだと思うけど…でも、もう自由になっていいんだよ」
「お前、何言って…」
「私も、こんなんじゃ、いつまでたっても土浦君に甘えちゃう。だからそろそろ頑張ってひとり立ちしなきゃ。それに私がずっと側にいたら、土浦君彼女1人つくることもできないでしょ。せっかくもてるんだから、勿体無いよ。だから、ね」
「香穂!!」
常にない口調で強く名前を呼ばれ、思わず言葉を止め、ビクリと体をこわばらす。
いつの間にか香穂子の方に向き直った土浦に、至近距離で両肩を掴まれる。
咄嗟に見上げた彼の表情は、今まで見たこともないほど苦しげに歪んでいて。
自分が彼にそんな顔をさせているのかと思うと、意味もなく泣きたくなってくる。
「お前、何を言ってるんだ。…俺と別れたいって、そういうことなのか…?」
「何言って…最初から付き合ってなんか…いないじゃない…?」
返ってきたのは予想外の彼の言葉で、何が何だか分からずにしどろもどろに言葉を繋ぐ。
「………」
「…だって、好きだって、言ってくれたことない…。私のこと、彼女なんかじゃないって、言ってたじゃない…っっ!」
言っているうちに、気持ちが高ぶってきて、ボロボロと涙が零れた。せめて最後くらいは「いい女」で終わらせたかったのに、格好悪い。
「…お前、あの時の会話、聞いてたのか…」
「…っ」
肯定と取れる土浦の言葉に、ゆるゆると絶望が押し寄せる。
…ああ、やっぱり私は、土浦君にとって「彼女」なんかじゃなかったんだ。
「…もう、離して…っ」
耐え切れず、しゃくり上げながら、土浦の手から逃れようと暴れる香穂子を、宥めるように、大きな手が髪を撫でる。そしてそのまま、その手が背に回ったかと思うと、息も出来ないくらいの強さで、強く抱きしめられた。
「…っ」
「…悪い。不安に、させてたんだな…」
「土浦く…」
熱い吐息が、耳朶をくすぐる。
好きな人から与えられたはじめての熱に、頭の中が真っ白になる。
「あの時の会話はそういう意味じゃなかったんだ。『寂しい時はいつも側で支えてくれる彼女』。俺と、お前の関係はそんな一方的なものなんかじゃなくて。どちらが欠けてもいけない。互いに支えあっているんだと、そう言いたかっただけなんだ」
「…え…」
「俺の言葉が足りなかったのが悪かったんだ。…悪い。もう、1人で泣かせたりなんかしないから、だから、こっちを向いてくれないか」
常にない、弱々しい彼の呼びかけに、恐る恐る、涙でグチャグチャになった顔をあげる。
「…ひどい、顔でしょ?」
「…いや、可愛い」
言ってから恥ずかしくなったのだろう。思わず目を逸らして頬を染める土浦の姿に、クスリと笑いがこぼれる。
そんな香穂子の様子に、土浦もまた、ほっとしたように表情を緩めた。
「やっと笑ったな。…香穂、いいか、こんなこと、滅多に言わないからよく聞けよ」
「……」
言って、そっと香穂子を抱きしめていた腕を緩めると、真剣な表情で向かい合う。香穂子も息を詰めて居住まいを正す。
「…お前が、好きだ」
「…っ」
そっと、囁くように。噛み締めるように、落とされた、言葉。
瞬間。呼吸が止まる。
幸せで。幸せで。クラリと眩暈がする。
「好きでいて…いいの?」
「いてくれ」
間髪空けずに告げられて。
「頼む…」
再び、背中に回された、大きな手のひら。
息も出来ない程の強さで抱きしめられる。
温もりと一緒に伝わってくる、微かな震えにに、泣きそうになる。
どうしようもなく溢れてくる、愛おしさ。
「うん…」
頷いた拍子に、堪えていた涙が再びあふれ出した。
そしてふいに思い出す。
彼の言葉。
――コンクールは終わったけど……終わらせたくないものもあるよな。そう思わないか?
あれは、最終コレクション直前のこと。
しっかり目線を合わせ、穏やかな笑みを湛えて告げてくれた。
その眼差しを、言葉を。
信じられなかったのは、他ならぬ自分自身だ。
…けれどまだ、遅くはないと。この温もりが教えてくれた。
「ありがとう…」
呟くと、瞼に、頬に、額に降り注いでくる、温もり。
――彼を好きでい続ける限り。きっと、これからも、不安な気持ちはなくなったりはしないけれど。
「…ね、土浦君。もう1曲、リクエストしてもよいかな」
「ああ、かまわないぜ」
「じゃあね…」
「「愛の挨拶」」
2人、重なった声に、視線を見交わして微笑みあう。
満ちる想いに感じる幸せ。
大切なものは確かにここにあると、今なら信じられるから。
不安も痛みもすべて抱きしめて。
――希う。
終わることのなく、続いていく――輝ける想いを。
●小説サイトにしたいのに、イラストしかない!…慌てて書き上げた「コルダ」創作第一作。気に入っていないので、そのうちさげるかも…。(苦笑)
ちなみに、タイトルは映画「ピアノ・レッスン」より、マイケル・ナイマン作曲「楽しみを求う心」から。クラシックではないですが、とても美しい旋律の曲でオススメです。
|