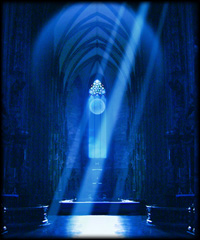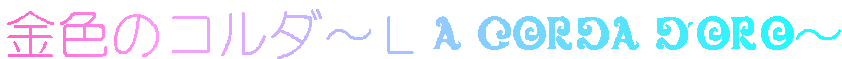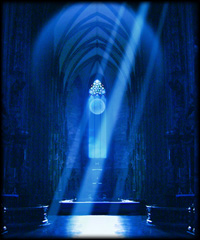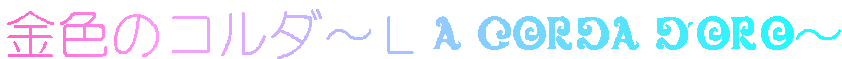――初めて彼女の音色を聞いたとき、心が震えた。
頭のてっぺんからつめの先まで。
僕を形作る、そのすべてが全身全霊で。
「彼女」が、「そう」なのだと。
そう、告げていた――。
※ ※ ※
「加地君」
放課後の教室で、友人たちと談笑していた加地は、おずおずと控えめに自身にかけられた声に、勢いよく顔を上げた。
「日野さん!」
傍目にも分りやすくパッと顔を輝かせ、「彼女」のもとに駆けていく加地の姿にも、周囲の友人たちも、もう見慣れたもので、むやみに冷やかすこともなく、ただ苦笑して見守るのみだ。
転校当初の周りの反応を思えば、随分と落ち着いたものである。
とはいえ、別に冷やかされたら冷やかされたで、加地にとっては、何ら困ることではないのだが、しかし、それによって「彼女」が変に萎縮してしまうのは非常に望ましくはない状況である。
現に、出会って間もない頃の香穂子は、周りの反応を気にして、加地と若干距離をおいている素振りがあった。
それゆえに、今現在の周りの気遣いを、今の加地としては、非常にありがたいものとして受け止めている。
「ごめんね、お話中邪魔しちゃって」
近くまで駆け寄ると、彼女の使っているシャンプーの香りがふわりと鼻をくすぐる。その香りに軽い眩暈を感じながらも、内心の動揺を押し隠して、微笑んで彼女に話しかける。
「ううん、気にしないで。僕にとって、他の誰よりも君の話が最優先なのは当然のことなんだから。それよりどうしたの?」
「う…うん、あのね、時間があったらこれから屋上で一緒に練習したいと思うんだけど、どうかな?」
「勿論、大丈夫だよ。それじゃあヴィオラを取ってくるから、ちょっと待っててくれる?」
「うん……ありがとう」
ふわり、と嬉しそうに微笑む香穂子を思わず抱きしめたい衝動にかられ、慌てて加地は一歩、距離をとる。
「加地君?」
「…あ、やっぱり先に屋上に行っておいてくれるかな。ちょっと用事を思い出して。僕も後からすぐに、行くから」
「え、うん…分かった。じゃあ、先に行ってるね?」
パタパタと軽い足音が遠ざかっていく音を、切ない表情で見送ると、脱力したように、廊下の壁にもたれかかり、一つ、大きな溜息をつく。
…初めは、ただ。その音色に惹かれた。
包み込みような、語りかけるようなその温かな音色に惹かれて。一目、その音色の主を見たくて。歩みを進んだその先に―――「彼女」がいた。
何よりもヴァイオリンを愛してやまないのだと傍目にみてもはっきり分かるほど、嬉しそうに、楽しそうにヴァイオリンを奏でる彼女の姿を目にしたその瞬間。
恋に―――落ちていた。
その微笑に、音色に、素直な心に。
あの日から、日1日と育っていった甘やかで、時に鋭い痛みすら伴うこの想いは、1人抱えるにはあまりにも大きくなりすぎて。
…もうとっくに、限界も間近なところまできている。
――けれど、まだ、彼女に告げるべき時ではない。
あと、2週間後にクリスマスのアンサンブルコンサートを控えている今。彼女の心を、無駄に波立たせるわけにはいかない。
彼女の音色は、とても素直だ。
良くも悪くも、感情が、そのまま音に出てしまう。
そしてそのことが、コンサートに悪影響を及ぼしてしまわないともかぎらない。
いつもいつだって、彼女には伸び伸びと音を奏でてほしいから。
だから、今はまだ言わない。――言えない。言えるはずが、ない。
けれど――。
先ほど、柔らかく香った彼女の残り香。
無防備な、無邪気な笑顔。
その一つ、一つが、少しずつ。しかし確実に自身を追いつめていく。
「…ふふっ、これは、思っていたよりキツイ……かな…」
自嘲気味に漏らされた、小さな小さな呟きは、誰にも聞きとがめられることはなく、冬の空気にとけていった。
※ ※ ※
そんな最悪な精神状態で、良い音色が出せるわけがなく。
内心の動揺は包みかくせず、音色になって表れてしまっていた。
「……ごめん、ミスばかりして、こんなのじゃ、練習にならないね。悪いけど、今日はここまでにしてくれるかな」
「え…」
驚きにパチパチと目を瞬かせ、こちらを見つめてくる日野から、思わず目を逸らす。
どんなことでも、以前の自分なら、もっと上手く立ち回れる筈だった。
それが、「彼女」が絡むと、途端にこの様だ。途轍もなく無様なものの……我ながら、どうしようもない。
「ごめんね、日野さん。コンサートも近いのに、君の足を引っ張って…」
自嘲気味にポツリと漏らした言葉。
優しい彼女が肯定する筈もないとわかっていながら、こんな言い方をするのは卑怯だと分かっている。
けれど、零れてしまう本音を止める術を知らず、深く俯く。
「加地君…」
誰よりも愛しく、大切にしたい少女を、他ならぬ自分が困らせている。
…情けないことこのうえない。
アンサンブルコンサートに参加を表明したその時から、遅かれ早かれ、こうなることは、分かっていたではないか。
―――「天賦の才」
自分が、いくら足掻いて。焦がれても。手に入れられない、ソレを。
当たり前のように享受している彼ら。
それでも、幼い頃は、努力次第で、ソレが手に入るのだと、信じて疑わなかったこともあった。けれど。
やがて、絶望とともに思い知った。
どんなに希求しても、手に入らぬものがあることを。
……それでも、音楽の道を絶つことは、未練がましくも出来なくて。
今もまだ、一縷の望みを捨てきれずにしがみついている。
……醜い、自身の音楽。
|